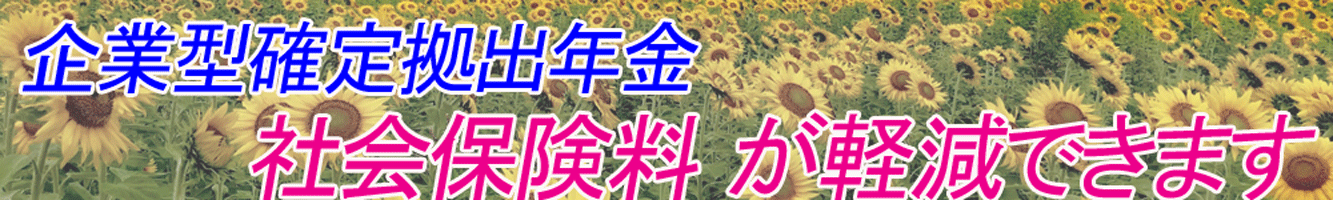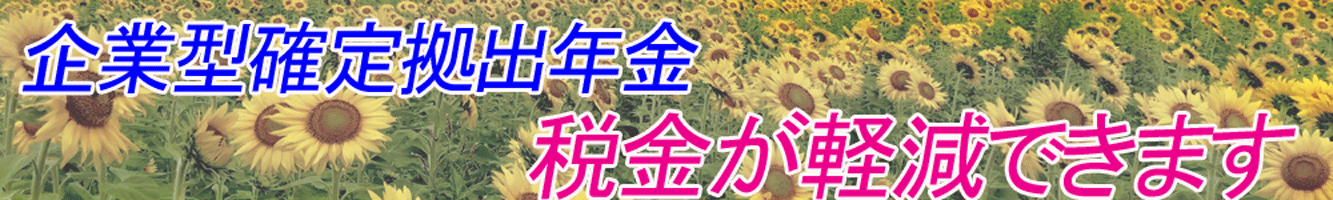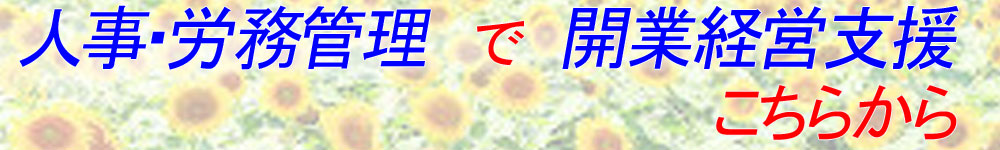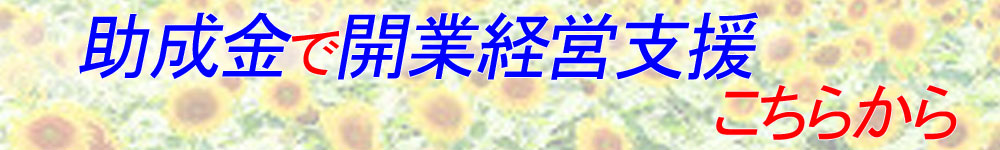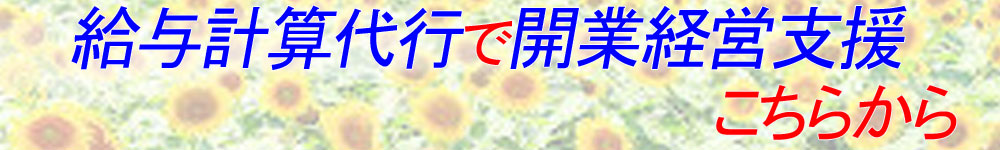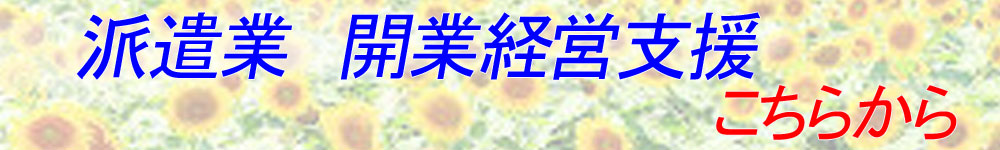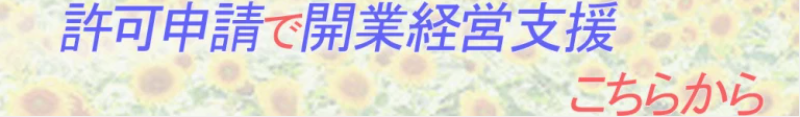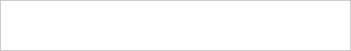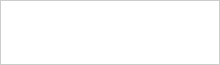株式会社設立の流れ
ひまわり事務所に株式会社設立代行のご相談・ご依頼を頂いてから 実際に株式会社を設立するまでの流れについてご説明いたします。
株式会社設立の流れ
(1) 株式会社の設立基本事項を決める
↓
(2) 株式会社の印鑑を作成する
↓
(3) 定款を作成する
↓
(4) 定款の認証をする
↓
(5) 資本金を払込む
↓
(6) 登記申請をする
下記にご説明いたします。
株式会社設立の流れ
(1) 株式会社の設立基本事項を決める
まず最初に、これから設立しようとする株式会社の基本的な事項を決めます。
株式会社設立 基本事項
① 商号
② 事業目的
③ 本店所在地
④ 出資額
⑤ 役員
⑥ 事業年度
⑦ 機関設計
株式会社設立 基本事項
① 商号
商号とは設立しようとしている株式会社の「名称」のことで、名前の前か後に「株式会社」を入れなければなりません
基本的に商号は、自由に決めることができますが、いくつかのルールがあり、そのルールに沿っていない商号は登記することが出来ません。
例えば、「同一住所、同一商号の禁止」というルールがあり、同一の住所に同一の商号を使用すると会社の区別が出来なくなるため、登記することは出来ません。登記所の類似商号調査簿にて確認する必要があります。
また銀行業でもないのに「銀行」という文字を使用したりするなど混乱を招くようなことは、不正競争防止法に抵触し、使用が禁止されています。
また、商号はブランディングにおいても大きく影響しますので、慎重かつ大胆に決めていくことをお薦めいたします。
株式会社設立 基本事項
② 事業目的
事業目的とは、設立しようとしている会社が行う予定の事業のことです。
法律上、事業目的に記載していない事業は行うことが出来ませんので、将来行う可能性がある事業内容もあらかじめ記載しておきます。
ただし、あまり多すぎると主たる事業が分からなくなりますので、多くても10項目程度が一般的です。
株式会社設立 基本事項
③ 本店所在地
定款や登記事項に定める、設立しようとしている会社の住所地を「本店所在地」といいます。
本店所在地は、登記事項なので本店所在地が変更したら変更登記をしなければなりません。
変更登記にもお金と時間がかかりますので、会社を設立しようとする場合、直ぐに引っ越さなければならないような所在地は避けた方が良いでしょう。
例えば、自宅を本店として定めるのも良いです。
本店所在地と事業所所在地とは違いますので、本店所在地を自宅や実家にして、事業所所在地をテナントなどの賃貸物件にするのも良いかと思います。
但し、賃貸の場合、契約書に「法人不可」となっていないか確認して下さい。
株式会社設立 基本事項
④ 出資額
出資額とは、設立しようとしている会社の資本金のことです。
発起人は、設立時の株式を一株以上引き受けないといけません。
株式会社の場合は最低額は1円となっていますが、一般的には3〜6か月程度の期間に純利益がなくても事業を続けていける額とされています。
ただし、許認可事業の場合は、要件に資本金の額が定められていることがありますので、事前に確認して下さい。
株式会社設立 基本事項
⑤ 役員
会社を設立時に、実際に会社運営をする役員(取締役、代表取締役や監査役など)を選任します。
役員の人員は任意ですが、設立する会社に取締役会を置くか否かによっても違ってきます。
取締役会を置かない場合は、取締役は1名いれば大丈夫です。
取締役会を置く場合は、取締役は3名以上にする必要があります。
株式会社設立 基本事項
⑥ 事業年度
株式会社を設立した場合、法律で決算書の作成が義務付けられています。
事業年度(決算期)は、1年以内であればその期間を自由に決めることができます。
会社計算規則において、会社の事業年度は、1年を超えてはならないと定められています。
株式会社設立 基本事項
⑦ 機関設計
株式会社設立するに当たり、最初にしなければならないのが株式会社の機関設計です。
株式会社の機関とは、会社法によって定められた機関のことで全部で10種類あります。
この株式会社の機関を、どのように設置するかを決める事を株式会社の機関設計と言います。

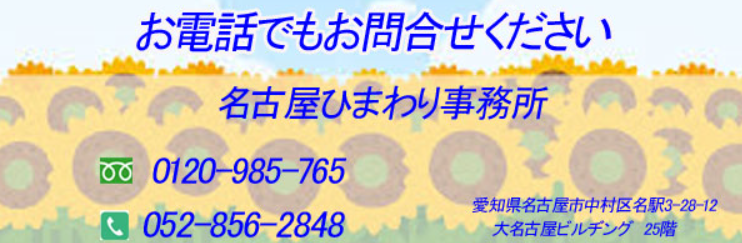
株式会社設立の流れ
(2) 株式会社の印鑑を作成する
株式会社の設立基本事項の内、会社商号が決まりましたら、会社代表者印を作りましょう。
印鑑は注文をして出来上がってくるまでに時間がかかる場合もありますので、早めに準備されることをお薦めいたします。
株式会社の設立登記を行う際に、会社の代表者印も登録し、その印鑑で会社設立登記申請書に押印します。
印鑑は、会社代表者印があれば会社設立はできますが、3点セットと呼ばれる下記の印鑑も併せて作ったりします。
設立時によく作られる会社印鑑
① 代表者印 (丸印)
② 銀行印
③ 角印
会社の印鑑
① 代表者印 (丸印)
設立しようとする会社の実印のことです。
法務局への届け出が必要になります。
契約書や官公庁への届け出など、正式文書に使用します。
通常、二重の同心円になっていて小円の中に「代表取締役之印」、大円と小円間の環状の部分に社名が彫られています。
会社の印鑑
② 銀行印
金融機関に届け出たもので、銀行と取引をする際に必要となります。
預金の払戻し、手形や小切手の振り出しなどに使用します。
上記の代表者印と銀行印を兼用することもできますので、絶対必要な印鑑ではありません。
会社の印鑑
③ 角印
会社代表者印よりやや大きめの、法人名だけを彫った四角い判子です。
ビジネス文書や注文書、納品書など、社外文書に使用します。
あってもなくてもどちらでも構いません。
株式会社設立の流れ
(3) 定款を作成する
定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたものです。
定款は会社法により記載する内容が、次のように定められています。
定款に記載されていないと定款全体が無効となってしまう事項
② 相対的記載事項
それについて決めたときには必ず記載しなければならない事項
③ 任意的記載事項
記載してもしなくてもどちらでもよい事項
上記の内、① 絶対的記載事項についてご説明します。
株式会社の定款 絶対的記載事項
ⅰ 事業目的
ⅱ 商号
ⅲ 本店の所在地
ⅳ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
ⅴ 発起人の氏名または名称及び住所
絶対的記載事項
ⅰ 事業目的
事業目的には、設立する会社の事業内容を記載します。
事業目的を設定する一番の目的は、「取引の安定性」のためですが、事業目的の決定に際して決めるべきポイントは3つ必要となります。
適法性とは、その名の通り会社設立の目的となる事業目的が違法ではないことを指します。
例えば「詐欺」「麻薬の輸入」など公序良俗に反する事業目的の内容は認められないこととなっています。
・ 営利性
会社の設立は利益をあげることを事業目的としなければなりません。
そのためボランティア活動や寄付活動は非営利の事業目的とすることはできません。
・ 明確性
事業目的は、どんな人が見てもわかるように設定する必要があります。
そのため事業目的は一般的にわかるものにする必要があります。
営業の許可がいる場合
設立しようとしている株式会社が、許可や指定が必要な業種だった場合、事業目的の記載には注意が必要です。
事業の内容だけではなく、根拠となる法律名まで記載した細かい文言まで記載が必要な場合がありますので注意が必要です。
設立しようとしている株式会社の定款記載 事業目的の具体例は、こちらをご参考にしてください。
絶対的記載事項
ⅱ 商号
原則として商号は自由に選ぶことができます。これを難しい言葉で商号選定自由の原則と言います。
しかし、いくつか注意点がありますので下記に記載します。
商号の決め方 注意点
① 商号の中に「株式会社」という文字を含めること
会社名の前か後ろに「株式会社」という言葉を入れなくてはなりません。
「株式会社」という表記を、「かぶしきかいしゃ」や「K.K」「Ltd」「Inc」など、ひらがなやローマ字で表すことはできません。
商号の決め方 注意点
② 使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビア数字
ローマ字を使って複数の単語を表記する場合には、単語の間に空白を入れることができます。
商号の決め方 注意点
③ 使用できる符号は「&」「’」「,」「-」「.」「・」の6種類
6種類の符号のうち「.(ピリオド)」は省略を示すものとして商号の末尾に使用が可能です。
それ以外の符号は、商号の先頭または末尾に使用することはできません。
商号の決め方 注意点
④ 法令により使用を禁止されている文字の使用の禁止
「銀行」「信託」「証券」「保険」などは、法令で使用が禁止されていますので、商号として使うことはできません。
商号の決め方 注意点
⑤ 同一の本店所在場所における同一商号の登記の禁止
他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用いて、その本店の所在場所が他の会社の本店の所在場所と同じであるときは、登記をすることができません。
そのため、株式会社を設立しようとする場合は、同一商号の会社が本店所在地と同一場所に存在していないかどうかを調査する必要があります。
これを商号調査と呼んでいます。
絶対的記載事項
ⅳ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
株式会社を設立する場合に、設立時に出資される財産の額は、確定した金額でなくてもよく、「その最低額」を決定すればよいことになっています。
ただし、株式会社登記申請時には「資本金の額」を確定する必要があります。
絶対的記載事項
ⅴ 発起人の氏名または名称及び住所
株式会社設立の流れ
(4) 定款の認証をする
会社設立時に作成された定款のことを原始定款といいます。
この原始定款は、株式会社の場合、そのままの状態では定款としての効力はありません。
公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことではじめて効力を持ちます。
これを定款の認証といいます。
定款の認証は、株式会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行い、税金が印紙代として40,000円必要となります。
名古屋ひまわり事務所では、電子認証により定款認証を行いますので、印紙代4万円が不要になります。
株式会社設立の流れ
(5) 資本金を払込む
株式会社の設立には資本金が必要です。
現在の会社法では資本金は1円でも良いことになっていますが、1円起業はあまり現実的ではありません。
業種にもよりますが、100万円〜1,000万円ほどになることが多いようです。
ただし、資本金が1,000万円を超えると初年度から消費税が課税されますので注意が必要です。
(通常、設立初年度の会社は消費税が免除されますが1,000万円を超えるとこの特例は適用されないためです。)
資本金の出資方法には、お金以外の「物」による現物出資も可能です。
株式会社設立の流れ
(6) 登記申請をする
名古屋ひまわり事務所と提携しています司法書士が、株式会社の本店所在地を管轄する法務局へ、格安で会社設立登の記申請を行います。
書類申請日が株式会社の設立日になります。
約1週間から2週間で株式会社設立登記が完了します。
株式会社設立 名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
株式会社設立代行
株式会社設立代行
会社設立後の各種届出一覧
株式会社設立代行
個人事業主から法人成りへ
個人事業で経営されている方が、「会社を設立した方が良いのか?個人事業主のままの方が良いのか?」についてまとめました。
株式会社設立代行
定款 事業目的の記載例
最初に決めさせていただく内容です。「営業許可を取る際の事業目的の記載方法」についてまとめました
株式会社設立代行
定款認証 手数料の改定
【定款認証 手数料が改定になりました】は、こちらをご覧ください
株式会社設立代行
株式会社と合同会社との比較
「会社を設立することは決めたけど、株式会社設立がいいのか?合同会社設立がいいのか?」についてまとめました。
株式会社設立代行
株式会社の機関設計
まず最初に決めてもらうのが、【株式会社の機関設計】です。公開会社にするのか大会社にするのかによって設計内容が違ってきます
株式会社設立代行
株式会社の節税
株式会社設立代行
株式会社設立の流れ
合同会社設立代行 名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
合同会社設立代行
 【合同会社を設立】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
【合同会社を設立】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
合同会社設立代行
合同会社から株式会社への組織変更
【合同会社から株式会社へ変更】する場合の諸手続きは、こちらをご覧ください
合同会社設立代行
合同会社設立の流れ
一般社団法人設立代行 名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
一般社団法人設立代行
 【一般社団法人を設立】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
【一般社団法人を設立】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
一般社団法人設立代行
一般社団法人とNPO法人との比較
【一般社団法人とNPO法人との比較】は、こちらをご覧ください
一般社団法人設立代行
一般社団法人設立の流れ
NPO法人設立代行 名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
NPO法人設立代行
 【NPO法人を設立】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
【NPO法人を設立】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
NPO法人設立代行
NPO法人 収益事業とは
NPO法人設立代行
NPO法人 特定非営利活動とは
NPO法人設立代行
NPO法人設立の流れ
人事労務で独立開業サポート 名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
人事労務で独立開業サポート
社会保険料が軽減できます
人事労務で独立開業サポート
税金が軽減できます
人事労務で独立開業サポート
従業員の人事労務管理で開業経営サポート
人事労務で独立開業サポート
会社設立後に最初にすべきこと 社会保険の設置と加入
【会社設立後に最初にすべきこと 社会保険の設置と加入】は、こちらをご覧ください
人事労務で独立開業サポート
会社設立後に最初にすべきこと 労働保険の設置と加入
【会社設立後に最初にすべきこと 労働保険の設置と加入】は、こちらをご覧ください
人事労務で独立開業サポート
会社設立後に最初にすべきこと 労働条件通知書
【会社設立後に最初にすべきこと 労働条件通知書】は、こちらをご覧ください
名古屋ひまわり事務所では こんな記事も読まれています
名古屋ひまわり事務所の
会社設立代行 開業経営サポート
【会社設立】をして独立開業をお考えの方はこちらをご覧ください
名古屋ひまわり事務所の
助成金申請代行 開業経営サポート
【助成金受給】して独立開業をお考えの方はこちらをご覧くださいは、こちらから
名古屋ひまわり事務所の
給与計算代行 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
介護業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
障害福祉サービス 開業経営サポート
会社を設立して【障害福祉サービス】を始めたい方は、こちらから
名古屋ひまわり事務所の
建設業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
産業廃棄物収集運搬業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
派遣業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
職業紹介業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
運送業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
利用運送業 開業経営サポート
名古屋ひまわり事務所の
その他の許可申請 開業経営サポート
株式会社設立代行 独立開業サポート お問合せください
まずはお電話を
メールでも
所在地はこちら
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
電話:0528562848